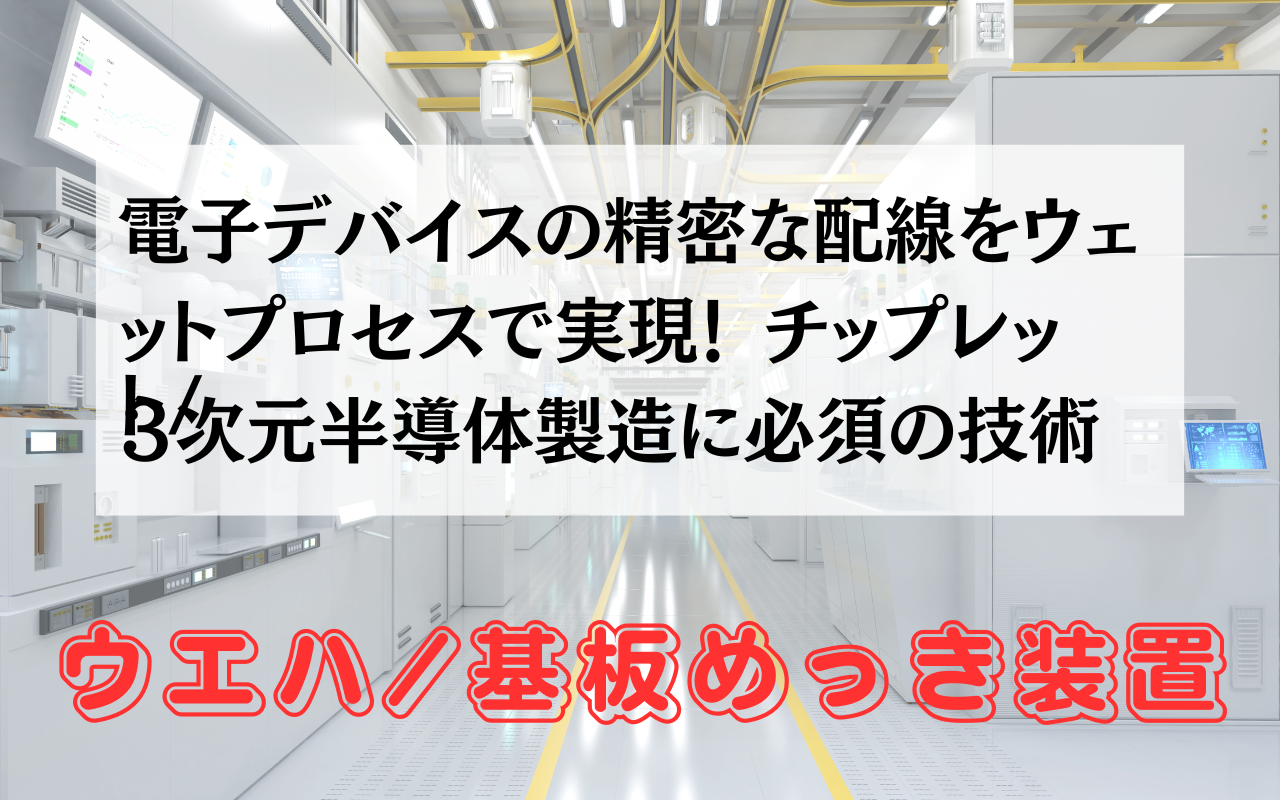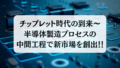半導体産業の要となるめっき装置。その市場規模は2030年までに驚異の74億2,000万ドルに達すると予測されています。本記事では、4インチ(100mm)から12インチ(300mm)のシリコンウエハや化合物ウエハ、さらには100mmから600mm角サイズの樹脂基板、ガラス基板に対応する電解・無電解めっき装置について、その定義から市場動向、種類、用途、主要メーカーまでを解説します。IoTやAI、5Gなどの先端技術を支える半導体製造の裏側で活躍するめっき装置の世界。その重要性と可能性をじっくりとのぞいてみましょう。
めっきには電解めっき(電気めっき)、無電解めっき(化学めっき)があります。半導体チップの多層配線(BEOL)には銅ダマシン、デュアルダマシンめっきが用いられています。電解めっきは主に配線や電極形成用途。銅めっき、金めっき、ニッケルめっき、銀めっき、スズ系はんだめっき、合金めっき、コバルトめっきなど。無電解めっきはニッケル/金めっき(Ni/Au)、ニッケル/パラジウム/金めっき(Ni/Pd/Au)がパワー半導体のアルミニウム下地膜の上の電極パッド(UBM)形成に用いられています。
めっき装置とは?
半導体製造における重要性
めっき装置は、半導体製造プロセスにおいて欠かせない重要な機械です。この装置を使用することで、シリコンウエハー上に絶縁膜や半導体膜といった薄膜を精密に積層形成し、複雑な電子回路の配線を作り出します。半導体デバイスの性能、信頼性、そして寿命を左右する重要な工程を担っているのです。例えば、最新のスマートフォンやコンピュータに搭載されている高性能チップの製造には、ナノメートル単位の精度で均一なめっき膜を形成できる高度なめっき装置が不可欠です。これらの装置なくして、現代のデジタル社会を支える半導体技術の進歩は考えられません。
めっき加工の基本原理
めっき加工の基本的な目的は、物質の表面に金属膜を形成することです。この技術は、耐食性や導電性、はんだ付け性などの機能性の向上を目的として広く利用されています。半導体製造では、主に銅やニッケル、金などの金属を用いて、ナノメートルレベルの微細な配線やバンプ(突起電極)を形成します。電解めっきでは、めっき液中に浸漬した被めっき物(陰極)と金属板(陽極)の間に電流を流すことで、陽極から溶出した金属イオンが陰極表面に析出します。一方、無電解めっきでは、化学反応を利用して金属イオンを還元し、被めっき物の表面に金属膜を形成します。これらの原理を応用し、半導体製造では複雑な回路パターンを高精度に形成しています。
めっき装置の進化
近年の半導体の高集積化・微細化に伴い、めっき装置も急速な進化を遂げています。例えば、1997年にIBMが発表した「電気銅めっき」技術とCMP(化学機械研磨)を組み合わせるCuダマシン法は、配線形成の革新をもたらしました。この技術により、従来のアルミニウム配線よりも低抵抗で高性能な銅配線の形成が可能になりました。現在では、5nm以下の超微細プロセスにも対応できる高度なめっき装置が開発されています。さらに、AIやIoTの発展に伴い、めっき装置自体にもスマート化の波が押し寄せています。例えば、リアルタイムでめっき状態をモニタリングし、最適な条件を自動調整する機能や、予知保全システムを搭載した次世代めっき装置の開発が進んでいます。これらの進化により、さらなる半導体の高性能化と製造効率の向上が期待されています。
めっき装置の市場規模
急成長する市場
世界の半導体めっきシステム市場は、2022年に約51億米ドルと評価されました。さらに驚くべきことに、2023年から2030年の予測期間にわたって4.8%を超える年間成長率(CAGR)で成長すると予想されています。この成長は、自動車分野における電子部品の使用量の急増と、5G通信やAI、IoTデバイスなどに使用される半導体の需要の爆発的な増加に支えられています。特に、自動運転技術やエレクトリックビークル(EV)の普及により、車載半導体の需要が急増しており、これがめっき装置市場の成長を強力に後押ししています。また、スマートフォンやタブレット、ウェアラブルデバイスなどの消費者向け電子機器の進化も、市場拡大の重要な要因となっています。
地域別の市場動向
アジア太平洋地域は、半導体メーカーの強い存在感や自動車および電子産業の急成長などの要因により、収益の面で市場を独占しています。特に、台湾、韓国、中国などの国々が、最先端の半導体製造技術と大規模な生産能力を持つことで、この地域の市場をけん引しています。例えば、TSMCやSamsungなどの大手ファウンドリーの存在が、アジア太平洋地域のめっき装置市場の成長に大きく寄与しています。一方、北米は、この地域の半導体セクターに対する政府の支援の増加などの要因により、最も急速に成長している地域となっています。米国のCHIPS法の施行により、国内での半導体製造への投資が加速しており、これに伴いめっき装置の需要も急増しています。欧州も、自動車産業のデジタル化や産業用IoTの普及により、着実な成長を見せています。
将来の市場予測
半導体製造用銅めっきソリューションの世界市場は、2024年から2030年の予測期間中にCAGR 8.67%で拡大し、2030年には8億2,934万米ドルに達すると予測されています。この成長は、5G通信インフラの整備、データセンターの需要増加、AIチップの普及などが主な要因となっています。特にアジア太平洋地域の成長が著しく、2030年には4億7,364万米ドルの市場規模に達すると見込まれています。この地域では、中国の半導体自給率向上の取り組みや、インドの「メイク・イン・インディア」政策による半導体産業の育成が、市場成長を加速させると予想されています。また、環境への配慮から、より効率的で環境負荷の低いめっきプロセスへの需要も高まっており、これが新たな市場機会を生み出すと期待されています。
めっき装置の種類
電解めっき装置
電解めっき装置は、外部電源によって駆動させる方式で、半導体製造プロセスにおいて広く使用されています。この装置は、数十μmもの厚膜めっきを形成する必要がある半田バンプめっきにおいて主に用いられます。電解めっきの利点は、めっき速度が速く、厚い膜を形成できることです。また、めっき条件の制御が容易で、均一な膜厚を得やすいという特徴があります。
しかし、電解めっき装置にはいくつかの課題も存在します。例えば、専用治具によるウエハへの外部電源取り付けが必要な上、めっき槽に投入するウエハ枚数が限られてしまいます。これにより、大量生産時の処理能力に制限がかかる可能性があります。また、複雑な形状の部品や絶縁体表面へのめっきが困難であるという欠点もあります。
最新の電解めっき装置では、これらの課題を克服するための技術革新が進んでいます。例えば、パルス電流を用いためっき技術や、めっき液の流動制御技術の導入により、より均一で高品質なめっき膜の形成が可能になっています。さらに、自動化技術の進歩により、ウエハの取り扱いや電源の接続を効率化し、生産性を向上させる取り組みも行われています。
無電解めっき装置
無電解めっき装置は、金属のイオン化エネルギー差で駆動する方式です。この方式の最大の特徴は、外部電源が不要であり、下地の金属膜が無くてもUBM(Under Bump Metal)層を形成可能な点です。無電解めっきは、金属露出部へ選択的な層形成が可能なため、レジストパターンが不要で、処理工数を削減できるという大きなメリットがあります。
無電解めっき装置は、特に以下のような場面で重宝されます:
- 複雑な形状の部品へのめっき
- 絶縁体表面へのめっき
- 均一な膜厚が必要な場合
- 微細な孔や溝へのめっき
最新の無電解めっき装置では、めっき液の組成や温度、pH値などを精密に制御することで、より高品質なめっき膜の形成を実現しています。また、環境への配慮から、より低環境負荷な無電解めっきプロセスの開発も進んでいます。例えば、有害な化学物質の使用を最小限に抑えためっき液の開発や、めっき廃液の再利用技術の導入などが行われています。
特殊めっき装置
特殊めっき装置は、特定の用途や要求に応じて設計された高度な装置です。これらの装置は、標準的なめっき装置では対応が難しい特殊な条件や形状に対応するために開発されています。
例えば、REEL to REEL コネクター部分めっき装置は、特殊液面制御の採用により、めっき精度±1.0mmという高い精度を実現しています。この装置は、フレキシブルプリント基板(FPC)やコネクターなどの連続的な部品のめっき処理に適しており、生産効率の向上に貢献しています。
また、短尺Agスポットめっき装置のように、他のレーンを停止することなく、めっきジグの交換ができる装置も開発されています。これにより、生産ラインの停止時間を最小限に抑え、生産性を大幅に向上させることが可能になっています。
さらに、最近では以下のような特殊めっき装置も開発されています:
- 3Dめっき装置:複雑な3D形状の部品に均一なめっきを施す装置
- 選択めっき装置:特定の部分のみにめっきを施す高精度な装置
- ナノめっき装置:ナノスケールの極めて薄い膜を形成する装置
これらの特殊めっき装置は、半導体産業だけでなく、医療機器、航空宇宙、エネルギー産業など、さまざまな分野で活用されており、技術革新の重要な役割を果たしています。
めっき装置の主な用途
半導体チップの配線形成
めっき装置は、半導体チップの配線形成に欠かせない重要な役割を果たしています。特に、現代の高性能半導体チップで広く採用されているCu(銅)配線では、デュアルダマシン法と呼ばれる革新的なプロセスが用いられており、ここで電解めっきプロセスが重要な役割を果たしています。
デュアルダマシン法の具体的なプロセスは以下の通りです:
- 層間絶縁膜に配線溝とビアホールを形成
- バリア層とシード層を成膜
- 電解めっきによる銅の埋め込み
- CMP(化学機械研磨)による余分な銅の除去
- キャップ層の形成
この方法により、微細で高性能な配線を形成することが可能になっています。例えば、最新の5nm以下のプロセスノードでは、線幅が20nm以下の超微細配線を形成することができます。これにより、チップの高性能化と小型化が実現され、スマートフォンやAIチップなどの先端デバイスの進化を支えています。
さらに、最近では配線材料としてコバルトやルテニウムなどの新しい材料を用いためっきプロセスの研究も進んでおり、さらなる微細化と性能向上が期待されています。
パッケージ基板の製造
ICが搭載されるパッケージ基板の積層配線工程及び最終表面処理にも、めっき技術が広く使用されています。パッケージ基板は、半導体チップと実装基板を電気的に接続する重要な役割を果たしており、その製造プロセスにはめっき技術
めっき装置の機器構成
- めっき槽(プレーティングセル): 電解めっきプロセスが行われる容器です。めっき槽は導電性の材料で作られ、めっき対象の基板(サブストレート)を収容します。めっき槽内にはめっき液が充填されます。
- 電解液供給装置: 電解めっきプロセスに使用する電解液(めっき液)を供給するための装置です。電解液供給装置は、めっき槽内のめっき液の濃度や温度を制御し、適切な条件下でのめっきを実現します。
- 電極: 電解めっきプロセスにおいて、基板にめっきする金属イオンを供給するための電極です。一般的には陽極(陽極バス)と陰極(基板)があります。陽極バスはめっき液内に配置され、めっきに使用する金属イオンを供給します。基板はめっき対象となる半導体ウエハや基板を指します。
- 電源: 電解めっきプロセスで使用する電力を供給するための装置です。電源は陽極バスおよび基板間に接続され、めっき液内の電流を制御します。通常は直流電源が使用され、電流の強度や極性を調整します。
- 測定・制御装置: 電解めっきプロセス中のパラメータを監視・制御するための装置です。めっき液の温度、電流密度、めっき時間などを測定し、制御します。温度計、電流計、タイマーなどが使用されることがあります。
- 添加剤補給装置: 電解めっきプロセスにおいて、めっき液に微量の添加剤を導入するための装置です。めっき液内のイオン分布や堆積特性を制御し、めっき膜の品質や均一性を向上させる役割があります。
めっき成膜原料
電解めっき液、無電解めっき液、めっき液添加剤、補給剤、前処理液、後処理液などが挙げられます。
めっき装置の主な製造メーカー
国内メーカー
日本国内では、荏原製作所、上村工業、EEJA、東設などが主要なめっき装置メーカーとして知られています。これらの企業は、長年の経験と技術力を活かし、高品質なめっき装置を提供しています。
海外メーカー
海外では、ラムリサーチ、アプライドマテリアルズ、ASM パシフィック テクノロジ、クラスワンテクノロジーなどが主要なプレーヤーとして挙げられます。これらの企業は、グローバル市場で強い競争力を持ち、革新的なめっき装置を開発・提供しています。
・
参考サイト
- ウエムラ博士のめっき物語 第5話:半導体パッケージへのめっき | 上村工業株式会社
- めっき装置の今とこれから
- めっき装置 – 企業24社の製品とランキング – IPROS
- UI Science
- 半導体製造におけるめっき工程とは?種類や特徴、課題を解説 | 株式会社エビナ電化工業所
- 半導体製造におけるめっき技術とは?種類や特徴、最新動向を解説 | SEMI-NET
- 電解めっき装置 | 株式会社荏原製作所
- 半導体パッケージ基板用めっき | 田中貴金属グループ
- 半導体めっき装置市場規模は2030年までに74億2,000万ドルに達すると予測 – 最新予測
- 半導体製造用銅めっきソリューションの世界市場:2024年
- 清川メッキ・めっきのKIYO科書