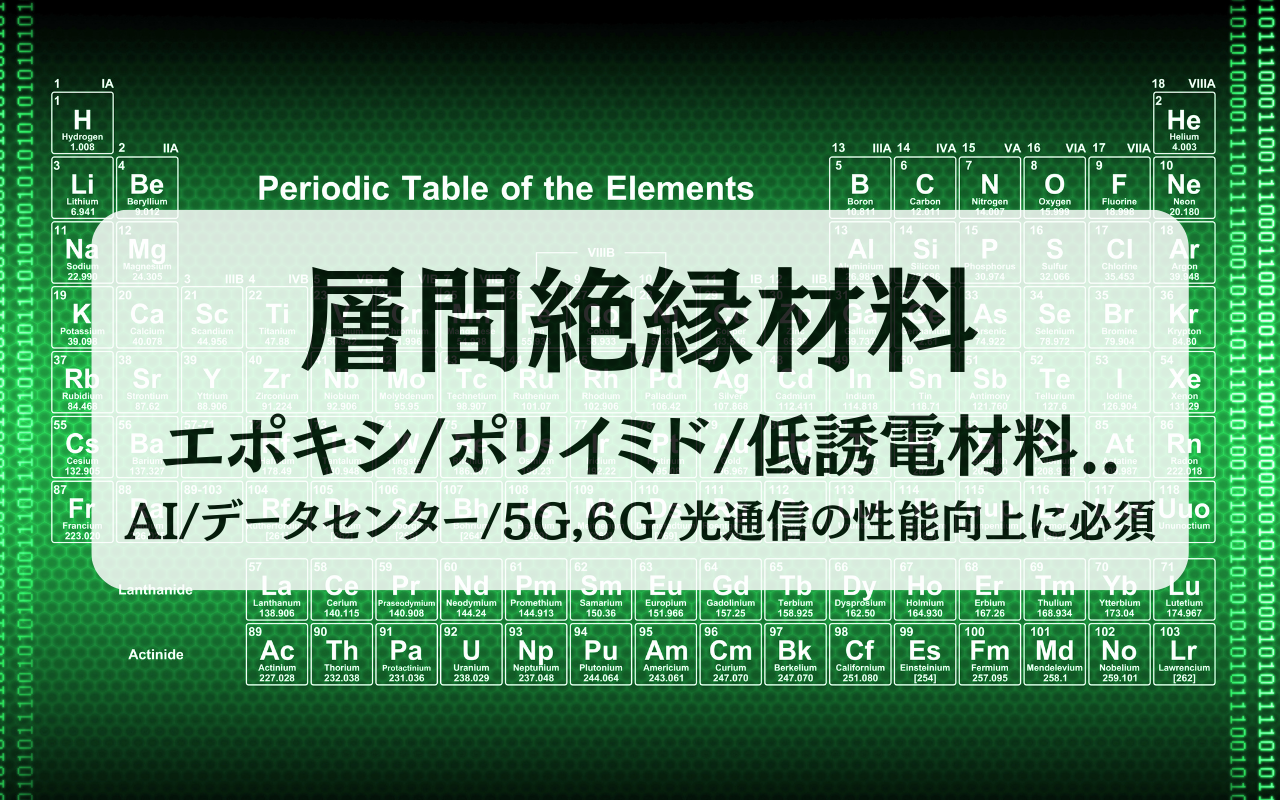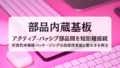半導体産業の急速な発展に伴い、層間絶縁材料の重要性が増しています。本記事では、層間絶縁材料の最新動向から市場規模、種類、用途、主要メーカーまで、エンジニアが知っておくべき情報を徹底解説します。
- 層間絶縁材料に関する最新ニュース
- 層間絶縁材料とは?
- 層間絶縁材料の市場規模
- 層間絶縁材料の種類
- 層間絶縁材料の主な用途
- 層間絶縁材料の主な製造メーカー
- 日本の材料メーカー
- 味の素ファインテクノ:ABF(Ajinomoto Build-up Film)
- 太陽インキ製造:熱硬化型絶縁材料ドライフィルム(Zaristo700)
- JSR:先端実装材料
- 東レ:半導体・電子部品向けポリイミド材料
- レゾナック:再配線用 感光性絶縁材料
- 住友ベークライト:半導体パッケージ基板材料
- 旭化成:パイメル
- UBE:ユーピレックス
- カネカ:超耐熱ポリイミドフィルム アピカル/ピクシオ
- ゼノマックスジャパン:高耐熱性ポリイミドフィルム ゼノマックス
- 富士フイルム:ポリイミド・ポリベンゾオキサゾール(PBO)材料
- 三井化学:ハイブリッド接合向け低温接合材
- 東レ:ハイブリッドボンディング(微細接合)に対応した新規絶縁樹脂材
- 日本の材料メーカー
- まとめ
- 参考サイト
層間絶縁材料に関する最新ニュース
BEOL用途、半導体パッケージ用途それぞれについての最新ニュースです。
BEOL用(ウェハ上のバックエンド・インタコネクト向け材料)
- 研究:SiCOHの次を目指す高熱伝導・極低k材料—RFIによるR&Dロードマップ(2025年7月)
米国のNatcastが発表したRFIで、k ≈ 1、熱伝導率 κ > 1.5 W/m·Kを備えた低k ILD材料(例:多孔質COF₂系ポリマーなど)が求められており、研究開発の方向性が示されています。
Natcast - BEOL向け新材料:IBMの「Advanced Low-k(ALK)」—PID耐性・Cu拡散バリア性・信頼性の強化(2024年頃)
IBMが紹介したALK(先進低k材料)は、従来のSiCOHを超える機械的強度、プラズマ損傷耐性(PID)、Cu拡散抑制性能を持ち、信頼性(TDDB)も向上しています。
IBM Research - 理論・実証研究:α-BN(アモルファスホウ素窒化物)をCu拡散バリア材に—超低誘電率の可能性
α-BN が ultrathin Cu拡散バリアとして注目されており、理論シミュレーションおよび実証試験では高い拡散防止効果と低誘電率が確認されています。
arXiv - 信頼性課題の解析:FCCSP構造での低k材料に伴う熱ストレスとクラックリスク評価
Flip-chip CSP構造におけるBEOL層は、熱サイクル時に低k材料でセパレーションやクラックが発生しやすいという解析結果。EMC厚、下填材のCTE、PI開口サイズが影響することも指摘されています。
MDPI
パッケージ基板用(ABFなど含む)
- ABF基板の役割と普及領域—高密度インターコネクトやAI/HPCパッケージを支える材料
ABFは高性能ICパッケージで不可欠な層間絶縁材料として、高密度配線、高信号整合性、熱安定性を実現。AI/HPC関連のパッケージで不可欠な存在として注目されています。
PCB Make Cadence PCB - ABF基板市場の現状と競争:Ajinomotoが優位だが、新規参入も活発化
世界市場において、Ajinomotoによる領導は続く一方で、中国などからの新規参入が増加。技術的には8µm以下の微細配線技術や、ガラスコア基板の台頭も観測されます。地政学的リスク対応として、米国での現地生産も進展しています。
先進技術市場調査 - 台湾サプライヤーの回復:AI駆動需要でUnimicron、Kinsusなどが回復基調に
2024年のAI需要拡大を受け、Unimicron、Kinsus、Zhen Ding Techなど台湾の主要IC基板メーカーが二桁成長を記録。Nan Ya PCBは苦戦も一部見られるとのことです。
DIGITIMES Asia - 先端パッケージ向けCu-to-Cuハイブリッドボンディングと対応材料のトレンド
IDTechExによるレポートでは、2.5Dおよび3DパッケージにおけるCu-Cuハイブリッドボンディング技術の普及に伴い、有機/無機誘電材料、インター・ポーザやRDLの材料選定が重要視されています。
IDTechEx - 旭化成 感光性絶縁材料(感光性ポリイミド)製品「パイメル™」の生産能力増強
先端半導体の高度化に伴い層間絶縁膜市場は拡大しています。旭化成の「パイメル™」は技術力・品質保証・顧客対応力を強みに高い競争力を持っています。特に生成AI向け市場は年8%の成長が続く見通しであり、需要増に対応するため2024年12月に静岡県富士市で新工場を竣工。今後も生産能力をさらに増強していく計画です。
近年の層間絶縁材料の開発動向を俯瞰すると、ウェハ内部のBEOL用材料とパッケージ基板用材料の両面で、それぞれ異なる課題に応える形で革新が進んでいることが分かります。
BEOL領域では、AIやHPCに代表される大規模演算需要の拡大を背景に、さらなる低誘電率化と高熱伝導性の両立が強く求められています。従来のSiCOH系材料では性能限界が意識され始めており、IBMによる先進Low-k材料や、α-BNを用いたCu拡散バリアの研究など、新たな材料群の探索が進んでいます。同時に、低k材料特有の機械的脆弱性やプラズマ損傷といった信頼性課題も顕在化しており、強靭性と信頼性を備えた次世代ILDが不可欠となっています。
一方、パッケージ基板では、Ajinomotoが独占的地位を築くABFが依然として標準材料であるものの、AI・HPC需要による急激な需要増により、供給体制の逼迫が問題となっています。その結果、ガラスコア基板や低Dk/低Df誘電体といったABFに代わる新規材料の開発・導入が注目を集めています。また、3DパッケージやCu-to-Cuハイブリッドボンディングといった次世代実装技術の進展に伴い、絶縁膜にはこれまで以上に平坦性・低誘電率・熱安定性が求められるようになっています。加えて、地政学リスクの影響から、材料供給の地域分散や現地生産拡大といったサプライチェーンの再構築も進められています。
総じて言えば、層間絶縁材料の開発トレンドは、**「BEOLでは限界突破、パッケージ基板では多様化と供給強化」**という二つの軸に整理できます。いずれもAIやHPCといった先端アプリケーションの急拡大が背景にあり、次世代半導体の性能と信頼性を左右する基盤技術として、層間絶縁材料はこれまで以上に戦略的な位置づけを強めています。
層間絶縁材料とは?
層間絶縁材料の役割
層間絶縁材料は、半導体デバイスの配線層間を電気的に絶縁する重要な材料です。主な役割は、異なる配線層間の信号干渉を防ぎ、デバイスの電気的性能と信頼性を確保することです。具体的には、寄生容量の低減、クロストークの抑制、絶縁破壊の防止などの機能を果たします。
主要な特性
層間絶縁材料に求められる主な特性は以下の通りです:
- 低誘電率(Low-k):信号遅延の低減に不可欠
- 高絶縁性:リーク電流の抑制
- 熱安定性:プロセス温度や動作温度に耐える
- 機械的強度:チップの信頼性確保
- 平坦化特性:多層配線の形成を容易にする
- 低吸湿性:エレクトロマイグレーションの抑制、デバイスの長期信頼性向上
最近では、高周波伝送に対応するため、誘電率2.0以下の超低誘電率材料の開発が進んでいます。
形状と種類
層間絶縁材料は、主に以下の形状と種類に分類されます:
- 形状
- フィルム状:ABFなど
- 液状:感光性ポリイミド材料など
- 材料系
- 有機系高分子材料:エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、BCBなど
- 無機系材料:シリコン酸化膜(SiO2)、シリコン窒化膜(Si3N4)など
これらの材料は、用途や要求特性に応じて選択されます。最近では、有機・無機ハイブリッド材料など、新しいタイプの材料も開発されています。
感光性と非感光性の違い
層間絶縁材料には、感光性と非感光性の2種類があり、、製造プロセスによって感光性、非感光性が使い分けられています。感光性材料は、フォトリソグラフィーによってパターニングが可能で、微細な配線構造の形成に適しています。一方、非感光性材料は、レーザー加工などの別の方法でパターニングを行います。
層間絶縁材料は、半導体デバイスの性能と信頼性を左右する重要な要素です。
その基本構造は、有機系高分子材料を主成分とし、フィルムや液体の形状で提供されます。
エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの材料が使用され、それぞれ特有の特性を持っています。
層間絶縁材料の市場規模
現在の市場規模と成長率
2022年の層間絶縁材料市場は約4億5,000万米ドルでしたが、2029年には7億570万米ドルに達すると予測されています。年平均成長率(CAGR)は6.5%と、堅調な成長が見込まれています。
地域別の市場動向
アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めており、特に中国、日本、韓国、台湾の需要が高いです。北米と欧州も安定した成長を示していますが、新興国市場の拡大が今後の成長をけん引すると予想されています。
成長を牽引する要因
5G通信の普及、AIやIoTデバイスの増加、自動車の電子化などが市場成長の主な要因です。特に、高性能コンピューティング(HPC)向けの需要が急増しており、市場拡大を後押ししています。
層間絶縁材料市場は、半導体産業の発展と密接に関連しており、着実な成長を続けています。2022年から2029年にかけて、年平均6.5%という高い成長率が予測されており、市場規模は7億ドルを超える見込みです。地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードしていますが、新興国市場の台頭も注目されています。この成長を支えているのは、5G通信やAI、IoTなどの新技術の普及です。特に、高性能コンピューティング向けの需要増加が、市場拡大の大きな原動力となっています。これらの要因により、層間絶縁材料市場は今後も持続的な成長が期待されています。
層間絶縁材料の種類
有機系材料
有機系層間絶縁材料は、低誘電率と高い加工性が特徴で、広く使用されています。主な種類は以下の通りです:
| 名称 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| エポキシ樹脂 | – 優れた接着性 – 低コスト – 高い電気絶縁性 – 耐水性・耐食性 – 硬化剤の選択で特性調整可能 | – 一般的なパッケージ基板 – 電子部品の封止材 – プリント基板 – コーティング材 – 接着剤 |
| ポリイミド樹脂 | – 高耐熱性 – 優れた機械的強度 – 高い電気絶縁性 – 耐薬品性 | – フレキシブル基板 – 高温動作デバイス – 航空宇宙産業部品 – 電子部品の絶縁材料 – 高温用フィルム |
| ベンゾシクロブテン(BCB) | – 超低誘電率 – 低吸湿性 – 優れた平坦性 – 低応力 – 高い熱安定性 | – 高周波デバイス – MEMS – 光導波路 – 層間誘電体 – チップパッケージング |
この表は、各材料の主要な特徴、一般的な用途、および代表的な特性値を示しています。エポキシ樹脂は優れた接着性と低コストが特徴で、一般的なパッケージ基板に広く使用されています。ポリイミド樹脂は高い耐熱性を持ち、フレキシブル基板や高温動作デバイスに適しています。ベンゾシクロブテン(BCB)は超低誘電率と低吸湿性が特徴で、高周波デバイスやMEMSなどの先端技術分野で使用されています。
各材料は独自の特性を持ち、それぞれの用途に応じて選択されます。エポキシ樹脂は汎用性が高く、ポリイミド樹脂は高温環境下での使用に適しており、BCBは高周波特性が要求される用途に適しています。
無機系材料
無機系層間絶縁材料は、高い絶縁性と熱安定性が特徴ですが、誘電率は有機系より高めです。
主な種類は以下の通りです:
| 名称 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| シリコン酸化膜(SiO2) | – 高絶縁性 – 優れた熱安定性 | CMOS集積回路の層間絶縁 |
| シリコン窒化膜(Si3N4) | – 高い誘電強度 – 優れたバリア性 | – パッシベーション層 – エッチングストップ層 |
| 低誘電率SiOC膜 | SiO2より低い誘電率(k=2.5-3.0) | 先端ロジックデバイスの層間絶縁 |
これらの材料は、主にCVDやスパッタリングなどの成膜技術で形成されます。
ハイブリッド材料
有機・無機材料を組み合わせたハイブリッド材料も開発されています。
これらは両者の長所を併せ持つ高性能材料として注目されています:
| 材料 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| 有機シリカハイブリッド | 低誘電率(k<2.5)と高い機械的強度の両立 | 次世代ロジックデバイスの層間絶縁 |
| ナノコンポジット材料 | ナノ粒子添加による特性向上 | 高周波デバイス、パワーエレクトロニクス |
| 自己組織化ポーラス材料 | 超低誘電率(k<2.0)と高い機械的強度 | 5nm以下のプロセスノード向け層間絶縁 |
これらの新材料は、従来材料の限界を超える性能を実現し、次世代デバイスの開発を加速しています
層間絶縁材料は、その形状や特性によって様々な種類に分類されます。フィルム状材料の代表格であるABFは、高性能CPUの絶縁材料として広く使用されており、市場の大部分を占めています。一方、液状材料は、スピンコート法による均一な塗布が可能で、微細な構造にも対応できる利点があります。さらに、半導体の高性能化に伴い、低誘電率材料や超低誘電率材料の開発が活発化しています。これらの新世代材料は、信号遅延の低減や消費電力の削減に大きく貢献し、5GやAI時代の半導体デバイスに不可欠な存在となっています。材料の選択は、デバイスの性能や製造プロセスに大きな影響を与えるため、エンジニアにとって重要な検討事項となっています。
層間絶縁材料の主な用途
半導体パッケージング
半導体パッケージングにおいて、層間絶縁材料は以下のような重要な役割を果たしています:
| パッケージタイプ | 用途 | 要求特性 |
|---|---|---|
| フリップチップパッケージ | – アンダーフィル材 – 再配線層(RDL)の絶縁 | – 低誘電率 – 高流動性 – 高耐熱性 |
| BGAパッケージ | – コア材料 – ビルドアップ層の絶縁 | – 低熱膨張係数 – 高絶縁性 – 高接着性 |
| 2.5D/3Dパッケージ | – インターポーザの絶縁層 – TSV充填材 | – 低誘電率 – 高アスペクト比対応 – 低応力 |
これらのパッケージングプロセスでは、配線間の絶縁と平坦化が重要な課題となっており、高性能な層間絶縁材料の開発が進められています。
ABFの独占市場であるFC-BGAでは、セミアディティブ法により多層配線が形成されます。ABFをコア材に真空熱圧着し、熱硬化させ、レーザービア加工、デスミア、粗化、無電解Cuめっき、ドライフィルムレジスト(DFR)貼付け、露光、現像、電解Cuめっき、レジスト除去、シード層除去といった一連の工程を繰り返しビルドアップ多層配線板が製造されます。
チップレット技術
チップレット技術では、複数の小型チップを組み合わせて高性能システムを構築します。この技術において、層間絶縁材料は以下のような役割を果たします:
| 構成要素 | 用途 | 要求特性 |
|---|---|---|
| チップ間接続 | – マイクロバンプ間の絶縁 – アンダーフィル | – 超低誘電率 – 高信頼性 – 熱応力緩和 |
| インターポーザ | – シリコンインターポーザの絶縁層 | – 低誘電率 – 高アスペクト比対応 – 低CTE |
| パッケージ基板 | – 高密度配線層の絶縁 | – 低誘電損失 – 高周波特性 – 高解像度 |
チップレット技術の進展に伴い、より高性能で信頼性の高い層間絶縁材料の開発が求められています。
FO-WLP/FO-PLP
ファンアウトウェハレベルパッケージ(FO-WLP)やパネルレベルパッケージ(FO-PLP)では、層間絶縁材料が以下のように使用されます:
| 構成要素 | 用途 | 要求特性 |
|---|---|---|
| 再配線層(RDL) | – 配線間の絶縁 – 平坦化 | – 低誘電率 – 高解像度 – 低反り |
| パッシベーション層 | – 最表面の保護 | – 耐環境性 – 低応力 – 高接着性 |
| モールド材料 | – チップ埋め込み – パッケージ形成 | – 低熱膨張係数 – 高強度 – 低吸湿性 |
これらの先端パッケージング技術では、層間絶縁材料の性能が製品の性能と信頼性を大きく左右します。特に、5G通信やAIチップ向けの高性能FO-WLP/FO-PLPでは、低誘電率と高信頼性を両立する材料の開発が進められています。
層間絶縁材料は、半導体産業において多岐にわたる用途を持っています。半導体パッケージングでは、チップと基板間の絶縁を担い、電気的特性と信頼性の向上に貢献しています。特に高性能CPUやGPUでは、ABFフィルムが標準的に使用され、その性能向上に大きく寄与しています。近年注目を集めているチップレット技術では、複数のチップを効率的に接続するために、高性能な層間絶縁材料が重要な役割を果たしています。また、FO-WLPやFO-PLPなどの先進的なパッケージング技術においても、層間絶縁材料は再配線層の形成に不可欠であり、デバイスの小型化と高性能化を支えています。これらの用途の多様化に伴い、層間絶縁材料の重要性はますます高まっており、今後も技術革新が期待されています。
層間絶縁材料の主な製造メーカー
日本の材料メーカー
これらの日本企業は、高度な材料技術と品質管理により、世界市場で高い競争力を維持しています。特に、先端プロセス向けの高性能材料開発で優位性を発揮しています。
味の素ファインテクノ:ABF(Ajinomoto Build-up Film)
ABFは、ベースフィルム、ABF(エポキシ樹脂),カバーフィルムの3層構造からなり、樹脂成分と無機フィラーを混合し絶縁性ワニスとし、支持体に塗布、乾燥して製造されている。GX(エポキシ+フェノール)、GZ(エポキシ+シアネート)、GL(エポキシ+フェノーリックエステル)シリーズがあり、分子構造上の極性を抑えることで高周波特性の向上が図られている。
太陽インキ製造:熱硬化型絶縁材料ドライフィルム(Zaristo700)
電気特性に優れた熱可塑性樹脂であるPPEを変性し、新しい熱硬化型樹脂を合成し、これを用いた適正な配合を開発することで、電気特性、加工性、信頼性に優れた高周波対応熱硬化型フィルムを開発しました。このフィルムは既存基材用フィルムと同じく熱硬化型であるため、既存同等の加工性、信頼性を持ちながらも、熱可塑性PPEフィルムの強みである優れた電気特性を併せ持ちます。これにより、5G向けの電子回路基材や層間絶縁材などにより適したフィルムを実現。
JSR:先端実装材料
先端ロジック向け材料で高いシェア、EUV用材料でも注目されているフォトレジストメーカーJSRは、めっき用厚膜フォトレジスト ELPAC® THBシリーズ、感光性絶縁材料 ELPAC® WPR / FGシリーズ、低誘電樹脂材料 ELPAC® HC-G Series、感光性絶縁材料 PI シリーズなどをラインナップ。
東レ:半導体・電子部品向けポリイミド材料
非感光ポリイミド セミコファイン、感光性ポリイミド フォトニース、有機コア用
感光性ポリイミド材料STF-1000などをラインナップ。
レゾナック:再配線用 感光性絶縁材料
半導体パッケージの再配線層(RDL)の、絶縁部分を形成するための感光性樹脂材料 AR-5100シリーズを提供。
住友ベークライト:半導体パッケージ基板材料
低CTE、 高弾性率かつ、高信頼性の基板材料LαZシリーズをラインナップ。
旭化成:パイメル
半導体素子の表面保護膜、バンプ用パッシベーション層、再配線用絶縁層として、世界中の半導体メーカーで採用実績のある液状の感光性樹脂材料。 耐熱・耐薬品性、電気・機械特性に優れた素材で、次世代パッケージ技術の要求にも対応できる各種製品ラインナップ。
UBE:ユーピレックス
自社生産品であるBPDA(ビフェニルテトラカルボン酸二無水物)を原料とした、 独自組成の超耐熱性ポリイミドフィルム。特に寸法安定性、低吸水性、耐薬品性に優れる。
カネカ:超耐熱ポリイミドフィルム アピカル/ピクシオ
超耐熱性の高機能性フィルム。航空機や機関車等のモーターの耐熱性絶縁材料、ビデオやカメラなどの小型化を可能にしたフレキシブルプリント配線板の基板材料として使用される。
ゼノマックスジャパン:高耐熱性ポリイミドフィルム ゼノマックス
ポリマーフィルムで最高レベルの寸法安定性・耐熱性を有し、ガラス・シリコンウェハ・セラミックスの代替や複合化に適した材料。
富士フイルム:ポリイミド・ポリベンゾオキサゾール(PBO)材料
保護層、パッケージング前の「バッファーコート(緩衝層)」、または、再配線層(RDL)用の特殊な応力緩和コーティング層です。バッファーコート層は、バックグラインド、シンギュレーション、組立工程中のダメージから、仕上げ済みのダイを保護し、パッケージ歩留まりの向上、信頼性の向上、長寿命化を実現。再配線層の応用技術は、最先端パッケージング設計を可能に。
三井化学:ハイブリッド接合向け低温接合材
課題の多いCoW(チップオンウエハ)接合において、SiO2同士の接合の代わりに樹脂材料を使うことでパーティクルの影響なく高強度の接合を可能に。Cu配線を露出させたウエハ表面に接合材をスピン塗布、キュア後にCMPにより平坦化させた後に低温接合を行うプロセス。
東レ:ハイブリッドボンディング(微細接合)に対応した新規絶縁樹脂材
シンガポール科学技術研究庁における半導体分野の研究機関であるIME(Institute of Microelectronics)との連携により本材料をC2W方式のハイブリッドボンディングに適用することで、異種チップを一つのパッケージに実装するチップレットの歩留まりと信頼性向上を目指す。
層間絶縁材料の製造メーカーは、それぞれ独自の技術と製品ラインナップを持っています。
味の素ファインテクノは、ABFフィルムで市場をリードし、高性能CPUの絶縁材料としてほぼ独占的な地位を確立しています。その高い信頼性と性能が、世界中のパソコンメーカーに評価されています。
ポリイミドの材料メーカー各社は、半導体パッケージング向けの多様な絶縁材料を提供し、特に5G通信に対応した低誘電率材料の開発に力を入れています。これらのメーカーは、半導体産業の技術進化に合わせて、常に新しい材料開発に取り組んでおり、層間絶縁材料の性能向上と多様化を牽引しています。今後も、各社の技術競争が市場をさらに活性化させることが期待されています。
まとめ
層間絶縁材料は、半導体産業の発展に欠かせない重要な要素として、今後も進化を続けていくでしょう。技術革新の面では、低誘電率化や高耐熱性の追求が続けられ、半導体デバイスの性能向上に大きく貢献すると考えられます。
市場競争の観点からは、ABFフィルムの独占状態に変化の兆しが見られ、新規参入企業との競争が激化することで、さらなる技術革新と価格競争が促進されると予想されます。
また、環境への配慮も重要なトレンドとなっており、ハロゲンフリーやリサイクル可能な材料の開発が進んでいます。これらの動向は、層間絶縁材料市場全体の健全な発展を促し、より高性能で環境に優しい半導体デバイスの実現につながるでしょう。エンジニアは、これらの変化を注視し、最適な材料選択と設計を行うことが求められています。
参考サイト
- 味の素発「半導体材料」成功の秘訣、市場ニーズを先読みしパートナーと共創
- DUVレーザーで半導体基板に世界最小の穴あけ加工を実現 ―4法人で半導体後工程技術を開発―
- 中国テック事情:チップ国産化推進で、打倒「味の素」の動き
- 積水化学が先端半導体向け材料の生産能力増強、台湾に評価/分析拠点も新設
- Vol.15 “SESUB”モジュールと「部品内蔵回路技術」
- 旭化成が設立した、高い品質要求に応える半導体感光性絶縁材料の新品証棟とは?
- 先端半導体にDXで対応する電子材料や電子部品–旭化成のデジタルソリューション事業
- 積水化学が先端半導体製造用工程材料の増産を決定、台湾にはR&D拠点を新設
- 太陽HDが開発に邁進、半導体の三次元化を推進する高解像度感光性絶縁材料
- 2026年,機能性電子フィルム市場は2兆2,393億円 | OPTRONICS ONLINE オプトロニクスオンライン
- 味の素、海外食品と半導体材料が好調 – NNA ASIA・日本・食品
- 味の素、半導体材料でもう一つの「金メダル」
- 2024年の半導体材料の世界市場は需要回復に伴い、前年比9%成長
- 地味だけどすごいADEKA、DRAMに続き先端ロジック材料にも照準
- 世界の電気絶縁材料市場の規模、シェア、成長、傾向
- 半導体実装工程材料・副資材世界市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所
- 2024年版 半導体材料の世界市場を調査
- 半導体材料メーカーのJSR、米投資ファンドに売却へ 経営陣主導で
- 味の素ビルドアップフィルム(ABF)が支配する半導体業界
- 味の素株式会社事業説明会 ICT領域 ~ABFを軸にした成長戦略~
- 半導体材料市場、2029年に583億ドル規模へ
- 2024年版 半導体材料の世界市場を調査
- 2024年の半導体材料の世界市場は需要回復に伴い、前年比9%成長
- 2026年,機能性電子フィルム市場は2兆2,393億円 | OPTRONICS ONLINE オプトロニクスオンライン
- 2023年版 機能性高分子フィルムの現状と将来展望 エレクトロニクスフィルム編
- 半導体材料市場、2029年に583億ドル規模 富士経済予測
- 半導体材料・原料市場の動向
- 2024年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望
- 層間絶縁膜(inter-layer dielectrics) | 半導体用語集
- 層間絶縁膜(ILD : Inter – Level Dielectric、 IMD : Inter-Metal Dielectric) | 半導体用語集
- 味の素ビルドアップフィルム®(ABF)
- 味の素ファインテクノ株式会社 電子材料事業部
- 層間絶縁材料 – 味の素ファインテクノ株式会社
- 半導体パッケージ基板用層間絶縁材料の現状と動向
- 特集/エレクトロニクス実装技術の現状と展望 半導体パッケージ基板用層間絶縁材料
- FC-BGA基板向 ビルドアップフィルム NX04シリーズ(NX04H)、NQ07シリーズ(NQ07XP)
- 【味の素×半導体】味の素ビルドアップフィルムの凄さとは?
- 味の素ビルドアップフィルム®(ABF)とは?
- 絶縁材の種類について
- 感光性層間絶縁材料 Photo Imageable Dielectric Material
- 味の素ビルドアップフィルム®(ABF)
- 半導体塗布絶縁材料
- 絶縁材製造・メーカーの会社・企業一覧(全国)
- 絶縁材料の製品一覧
- 半導体パッケージ基板用層間絶縁材料の現状と動向
- 日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】
- 味の素ファインテクノ株式会社 電子材料事業部
- 旭化成株式会社
- 層間絶縁材料 – 味の素ファインテクノ株式会社
- 絶縁材メーカー33社
- FC-BGA基板向 ビルドアップフィルム NX04シリーズ(NX04H)、NQ07シリーズ(NQ07XP)