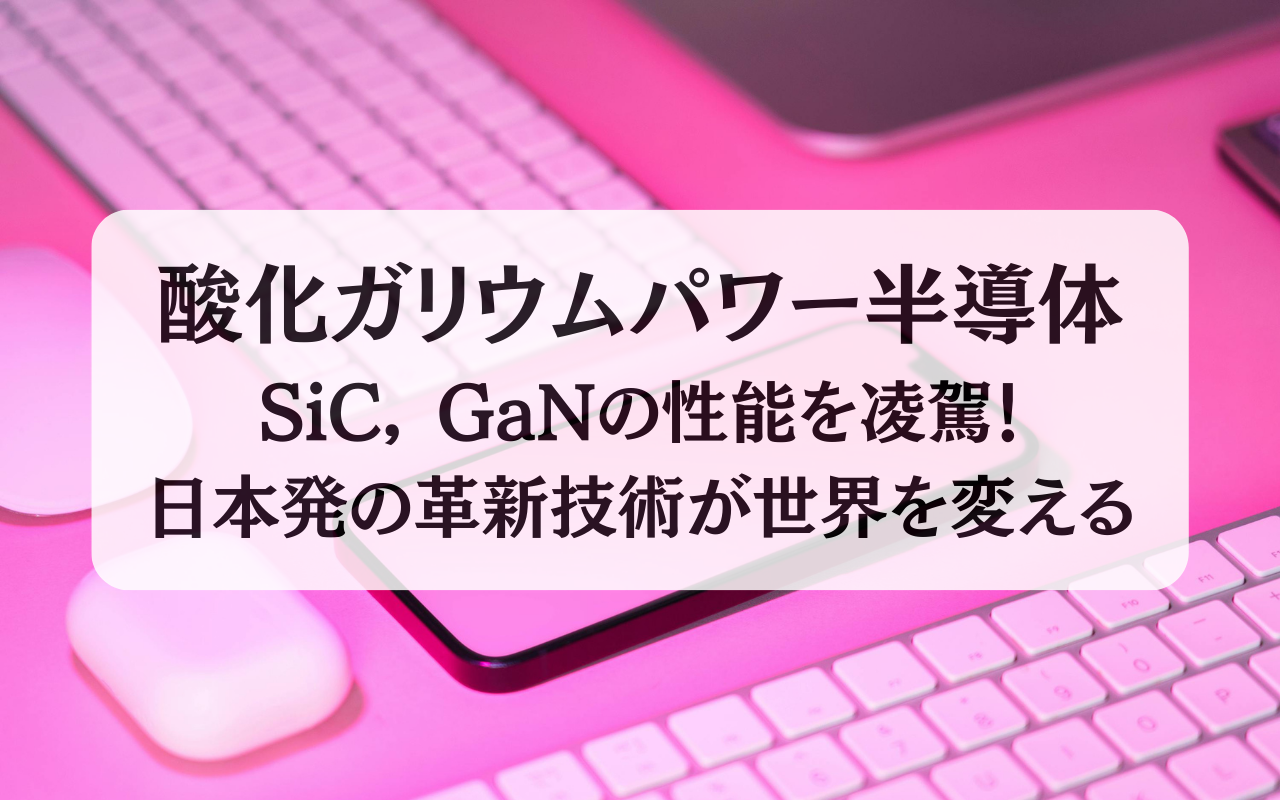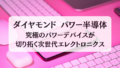酸化ガリウム(Ga2O3)パワー半導体は、従来のシリコン(Si)や炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)を超える性能を持つ次世代パワーデバイスとして注目を集めています。本記事では、酸化ガリウムパワー半導体の特徴、市場動向、技術課題、そして主要メーカーの最新の取り組みについて詳しく解説します。
酸化ガリウムパワー半導体関連の最新ニュース
- 東北大学発スタートアップFOXが新技術で量産化に挑戦
東北大学金属材料研究所の吉川彰教授らが設立した新会社「FOX」が、酸化ガリウムウエハーの低コスト量産化技術の実用化に乗り出しました。同社は、イリジウムるつぼを使わない単結晶育成技術「OCCC(オートリプルシー)法」を用いて、β-Ga2O3バルク単結晶の製造コストを既存の方法の100分の1程度に抑えることを目指しています。 - 日本企業が酸化ガリウム開発でリード
日本国内では、α型酸化ガリウムを京都大学発ベンチャーのFLOSFIAが、β型をタムラ製作所などが出資するノベルクリスタルテクノロジーが、基板とデバイスの開発を進めています。特にノベルクリスタルテクノロジーは2021年6月に世界初となる100ミリウエハの量産に成功し、研究開発用ウエハ市場でほぼ100%のシェアを獲得しています。 - 産総研が高放熱型酸化ガリウムパワー半導体の開発に着手
産業技術総合研究所(産総研)のデバイス技術研究部門は、酸化ガリウムの課題である低い熱伝導率を克服するため、高い熱伝導率を持つ炭化ケイ素(SiC)やダイヤモンド基板を活用した高放熱型酸化ガリウムパワー半導体の開発に取り組んでいます。この技術が実現すれば、酸化ガリウムパワー半導体の実用化が大きく前進すると期待されています。
酸化ガリウムパワー半導体とは?
広いバンドギャップを持つ次世代半導体材料
酸化ガリウム(Ga2O3)は、シリコン(Si)や炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)よりも広いバンドギャップを持つ半導体材料です。バンドギャップが広いほど、高電圧・高温での動作が可能になり、電力損失を低減できます。酸化ガリウムのバンドギャップは約4.8-4.9 eVで、シリコン(1.1 eV)の約4倍以上、SiC(3.3 eV)やGaN(3.4 eV)よりも20%以上大きいという特徴があります。
高い絶縁破壊電界強度
酸化ガリウムは、シリコンの約10倍、SiCやGaNの約2倍の絶縁破壊電界強度を持っています。これにより、同じ耐圧のデバイスを作る場合、酸化ガリウムを用いると活性層を非常に薄くすることができ、オン抵抗を大幅に低減できます。理論的には、シリコンの3000倍以上、SiCの8倍以上、GaNの4倍以上の性能指数(バリガ性能指数)を持つとされています。
低コスト製造の可能性
酸化ガリウムは、シリコンと同様に融液から単結晶を成長させる方法(融液成長法)で製造できるため、大口径のウエハを低コストで製造できる可能性があります。また、シリコンと同程度の硬度であるため、既存のシリコン用加工装置をそのまま使用できるというメリットもあります。これらの特徴により、将来的にはSiCやGaNよりも安価なパワーデバイスの実現が期待されています。
酸化ガリウムパワー半導体の市場規模
急成長が予測される市場
世界の酸化ガリウムパワー半導体市場は、2022年に757万米ドル(約7.63億円)と評価されており、2023年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)51.75%で成長し、2030年までに1億9,623万米ドル(約197.8億円)に達すると予測されています。この急成長は、酸化ガリウムの優れた特性と、パワーエレクトロニクス分野での高性能・高効率デバイスへの需要増加によるものです。
アプリケーション別市場シェア
酸化ガリウムパワー半導体市場は、アプリケーション別に電力・高電圧デバイス、エレクトロルミネッセンスデバイス、ガスセンサー、その他に分類されます。2022年時点で、電力・高電圧デバイス部門が市場シェアの42.36%を占めており、最大のセグメントとなっています。この分野では、酸化ガリウムの高耐圧特性を活かした高効率パワーデバイスの開発が進んでいます。
地域別市場動向
地域別では、アジア太平洋地域が2022年の世界市場で約37.35%のシェアを占め、2.85億米ドルの市場規模となっています。この地域は2023年から2030年にかけて57.12%のCAGRで成長すると予測されており、最も急成長する市場となる見込みです。一方、北米市場も51.07%のCAGRで成長すると予想されており、自動車産業や再生可能エネルギー分野での需要増加が期待されています。
酸化ガリウムパワー半導体の主な用途
電力変換装置
酸化ガリウムパワー半導体は、その高耐圧・低損失特性を活かし、電力変換装置での使用が期待されています。特に、電気自動車(EV)のモーター駆動用インバーターや、太陽光発電システムのパワーコンディショナーなどへの応用が注目されています。これらの用途では、高効率な電力変換が求められるため、酸化ガリウムの特性が大きな利点となります。
高周波デバイス
酸化ガリウムの広いバンドギャップと高い絶縁破壊電界強度は、高周波デバイスにも適しています。5G通信やミリ波レーダーなどの高周波アプリケーションでは、高出力・高効率な増幅器が必要とされており、酸化ガリウムを用いたトランジスタがその要求を満たす可能性があります。特に、現状のパワー半導体では制御できない高出力・高周波数の電力制御が可能になると期待されています。
産業機器・民生用電源
産業機器や民生用の小型電源にも、酸化ガリウムパワー半導体の応用が期待されています。例えば、データセンターのサーバー用電源や、スマートフォンの急速充電器などに使用されることで、電力変換損失を劇的に低減し、機器の小型化・高効率化に貢献する可能性があります。特に、データセンターの電力消費量削減は大きな課題となっており、酸化ガリウムデバイスの実用化が待たれています。
酸化ガリウムパワー半導体の主な種類
β型酸化ガリウム(β-Ga2O3)
β型酸化ガリウムは、現在最も研究開発が進んでいる酸化ガリウムの結晶構造です。モノクリニック構造を持ち、最も安定した形態とされています。β-Ga2O3は、融液成長法による大口径ウエハの製造が可能であり、低コスト生産の観点から注目されています。日本のノベルクリスタルテクノロジーが2021年6月に世界初の100mmウエハの量産に成功しており、研究開発用ウエハ市場でほぼ100%のシェアを獲得しています。
α型酸化ガリウム(α-Ga2O3)
α型酸化ガリウムは、コランダム構造を持つ結晶形態です。β型と比較してさらに広いバンドギャップ(約5.3 eV)を持つことが特徴で、理論的にはより高い性能が期待できます。しかし、安定性や製造の難しさから、β型ほど開発が進んでいません。日本では京都大学発ベンチャーのFLOSFIAがα型酸化ガリウムの開発を進めており、独自の技術で基板とデバイスの開発に取り組んでいます。
ε型酸化ガリウム(ε-Ga2O3)
ε型酸化ガリウムは、六方晶系の結晶構造を持つ形態です。β型やα型と比較してまだ研究段階にありますが、特定の結晶面で高い分極効果が得られる可能性があり、高周波デバイスへの応用が期待されています。ε型は、他の結晶構造と比べて安定性に課題があるため、現在は主に薄膜形成技術の開発や基礎的な物性研究が行われています。
酸化ガリウムパワー半導体の技術的な課題
熱伝導率の低さ
酸化ガリウムの最大の技術的課題は、熱伝導率の低さです。熱伝導率は、シリコンの約4分の1、SiCの約10分の1程度しかありません。これは、パワーデバイスとして使用する際に発生する熱を効率的に放散できないことを意味し、デバイスの性能や信頼性に大きな影響を与える可能性があります。この問題を解決するため、産業技術総合研究所(産総研)などの研究機関では、高い熱伝導率を持つSiCやダイヤモンド基板を活用した高放熱型酸化ガリウムパワー半導体の開発に取り組んでいます。
p型伝導の実現困難性
酸化ガリウムは、現状ではp型伝導の実現が非常に困難です。これは、バイポーラデバイス(pn接合を利用するデバイス)の作製が難しいことを意味し、応用可能なデバイス構造が限定されてしまいます。現在の開発は主にユニポーラデバイス(n型のみを使用するデバイス)に集中しており、MOSFETやショットキーバリアダイオードなどが中心となっています。p型伝導の実現は、酸化ガリウムデバイスの応用範囲を大きく広げる可能性があるため、継続的な研究が行われています。
結晶品質と欠陥制御
大口径ウエハの製造技術が進展している一方で、結晶品質の向上と欠陥制御は依然として重要な課題です。特に、融液成長法で作製された結晶には、酸素空孔や不純物などの欠陥が含まれやすく、これらがデバイス性能に悪影響を与える可能性があります。東北大学発のスタートアップFOXが開発を進めているOCCC法は、貴金属フリーの単結晶育成技術により、シリコンに匹敵する低欠陥のβ-Ga2O3インゴット/基板をSiCより安価に製造することを目指しています。この技術の実用化により、結晶品質の向上と製造コストの低減が同時に達成される可能性があります。
酸化ガリウムパワー半導体の開発メーカー
- ノベルクリスタルテクノロジー
ノベルクリスタルテクノロジーは、β型酸化ガリウム(β-Ga2O3)ウエハの開発・製造で世界をリードする日本企業です。2021年6月に世界初となる100ミリウエハの量産に成功し、研究開発用ウエハ市場でほぼ100%のシェアを獲得しています。同社はタムラ製作所などが出資しており、β-Ga2O3の基板とデバイスの開発を精力的に進めています。 - FLOSFIA
FLOSFIAは京都大学発のベンチャー企業で、α型酸化ガリウム(α-Ga2O3)の開発に特化しています。同社は世界初のGaO®ブランドでの商用レベルのショットキーバリアダイオード(SBD)のサンプル出荷や、α-Ga2O3に関連する特許を700件以上出願するなど、革新的な技術開発を行っています[6]。最近では、新規P型半導体である酸化イリジウムガリウムα-(IrGa)2O3を用いたジャンクションバリアショットキー(JBS)構造ダイオードの開発に成功し、酸化ガリウムのP層課題解決に向けて大きな進展を見せています。 - FOX
FOXは東北大学発のスタートアップ企業で、β-Ga2O3ウエハーの低コスト量産化技術の実用化を目指しています。同社は、イリジウムるつぼを使わない単結晶育成技術「OCCC法」を用いて、製造コストを既存の方法の100分の1程度に抑えることを目標としています。2028年内には6インチウエハーの量産技術確立を目指しており、大口径化によるコストメリットと生産性向上が期待されています。
まとめ
酸化ガリウムパワー半導体は、従来のシリコンや炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)を超える性能を持つ次世代パワーデバイスとして注目を集めています。日本の企業が技術開発をリードしており、ノベルクリスタルテクノロジー、FLOSFIA、FOXなどのスタートアップ企業が、それぞれ独自の技術で酸化ガリウムの高い潜在能力を引き出すための開発を進めています。
しかし、実用化に向けてはまだいくつかの課題が残されています。主な課題としては、P型層の実現、熱伝導率の低さを補う放熱技術の確立、結晶品質の向上と欠陥制御などが挙げられます[5][9]。これらの課題を克服することで、酸化ガリウムパワー半導体の市場は急速に拡大すると予測されており、2030年までに1億9,623万米ドル(約197.8億円)に達すると見込まれています。
今後、酸化ガリウムパワー半導体の実用化が進めば、電気自動車(EV)のモーター駆動用インバーターや太陽光発電システムのパワーコンディショナー、データセンターのサーバー用電源など、幅広い分野での応用が期待されます。これにより、エネルギー効率の向上や機器の小型化、低コスト化が実現し、持続可能な社会の実現に大きく貢献することが期待されています。
参考サイト
- 酸化ガリウム(Ga2O3)パワー半導体」関連銘柄を紹介! EVや再生可能エネルギーの普及で、今後大きな成長が期待できる「第3の次世代パワー半導体」とは!?
- 酸化ガリウムパワー半導体の最新動向
- 酸化ガリウムウエハーの低コスト量産に向け、東北大が新会社を起業
- 半導体酸化ガリウム市場規模レポート[2023-2030]
- 酸化ガリウムを用いた次世代パワー半導体の開発
- FLOSFIA、酸化ガリウムパワーデバイスの量産化に向けた新工場を設立
- 「GaNパワー半導体」関連銘柄は、省エネ&CO2削減に欠かせない”国策テーマ株”! 半導体市場で日本企業がシェアを拡大するカギとなる「次世代半導体」に注目!
- 酸化ガリウムを用いた次世代パワーデバイスの開発
- 次世代パワー半導体の最新動向
- FLOSFIAが酸化ガリウムパワーデバイスの量産化に向けた新工場を設立